税金の滞納は、単なる支払いの遅れだけでなく、延滞税が発生します。
それでもなお、滞納を放置すれば、最終的には財産の差し押さえという深刻な事態に発展するリスクがあります。
税金の滞納は、信用力の低下によって新たな融資が受けられなくなったり、キャッシュフローや事業運営にも影響が及ぼしたりするので注意が必要です。
本記事では、税金滞納のデメリットや、差し押さえに至るまでの流れ、そして差し押さえを回避するための具体的な対処法について解説します。
監修者プロフィール

急遽資金が必要になった、新規事業開拓のための資金が欲しい、経営状態に関する相談がしたい、そんな経営者の皆様を全力でサポートしています。
税金を滞納するデメリット

税金には納付期限があり、期限を過ぎると滞納となります。滞納が続くと、延滞税の発生や財産の差し押さえなど、納税者にとって不都合なことが生じるので注意しなければなりません。
以下では、税金を滞納することにより生じる5点のデメリットについて紹介します。
- 延滞税が発生する
- 財産の差し押さえリスクがある
- 信用力が低下する
- 新たな融資を受けられなくなる
- キャッシュフローや事業に影響が出る
延滞税が発生する
税金の納付期限を過ぎると、本税に加えて延滞税も支払う必要があります。
延滞税は納付期限の翌日から発生し、遅れた日数に応じて加算される仕組みです。
そのため、納付が遅れれば遅れるほど、最終的な支払額は増えてしまいます。
延滞税の税率は、延滞日数に応じて段階的に変動します。詳しくは以下の表をご覧ください。
| 延滞した日数 | 税率 |
| 納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで | 年7.3%または延滞税特例基準割合A(下記のA列の数字)+1%(※いずれか低い方) |
| 納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降 | 年14.6%または延滞税特例基準割合B(下記のB列の数字)+7.3%(※いずれか低い方) |
また、延滞税特例基準割合は次のようになっています。
【延滞税特例基準割合】
| 期間 | 延滞税特例基準割合A | 延滞税特例基準割合B |
| 令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
| 令和4年1月1日~令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
| 令和5年1月1日~令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
| 令和6年1月1日~令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
| 令和7年1月1日~令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
【延滞税特例基準割合とは】
延滞税特例基準割合は、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割って算出した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
(出典:国税庁「延滞税の割合」)
財産の差し押さえリスクがある
税金の滞納を放置していると、督促状が郵送されます。督促状が送付されているにもかかわらず、納税せず放置し続けると財産を差し押さえられるリスクがあるので注意が必要です。
財産は精査され、換金可能と判断された財産に対して、原則差し押さえを行います。
ただし、財産の中には、仕事や生計を立てるために必要とされるものは、差し押さえの対象外となります。
具体的に差し押さえ対象および対象外の財産は以下の通りです。
| 差し押さえ対象 | 差し押さえできない財産 |
| ・不動産・預貯金・貴金属類・機械など | ・衣服・寝具・生活に必要な3か月分の食料・燃料など |
注意点として、本来納めるべき税金は納めていても、延滞税のみの滞納でも、差し押さえられるリスクがあります。
また、転居している場合は旧住所に督促状が送られるため、気付かないうちに差し押さえられるといったことも発生する恐れがある点にも留意しましょう。
(出典:国税庁「第47条関係 差押えの要件」)
信用力が低下する
税金の滞納のデメリットとして、信用力が低下する点があります。遅延なく納税していたり、しかるべき手続きを取ったりしたりしている場合、外部に滞納の事実が知られるリスクは低いです。
しかし、差し押さえに至ると、外部に差し押さえの事実が知られることになり、取引先に知られると信用力の低下につながりかねません。継続取引だけでなく、自社の信用にも大きく影響を及ぼし、事業運営が厳しくなることが避けられなくなるでしょう。
新たな融資を受けられなくなる
税金滞納により、新たな融資が受けられなく点にも注意しましょう。金融機関で融資を受ける場合、申込時に納税証明書の提出が一般的とされています。税金滞納していると、未納となり、金融機関の審査に支障をきたします。
新たに融資を申し込む際には、事前に税金未納分を支払っておくか、あるいは別の資金調達方法で、税金の滞納を解消しておくようにしましょう。
キャッシュフローや事業に影響が出る
延滞税の上乗せにより、支払うべき税額が大きくなり、手元の現金も減っていくことが考えられます。
もし、滞納した税金を放置すれば、工場や機械などが差し押さえられ、差し押さえられると商品を生産することが難しくなるでしょう。
利益を生み出せず、ランニングコストなど出費ばかりが発生し、キャッシュフローはどんどん悪化していくことになり、事業の運営そのものが危ぶまれます。
税金滞納の時効は5年
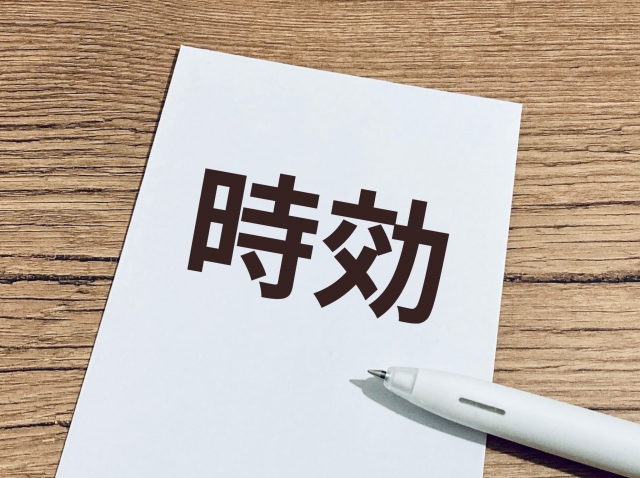
滞納した税金には、法定納期限(支払期限)から原則5年で時効が成立すると法律で定められています。しかし実際には、5年を経過しても納税義務が消滅することはほとんどありません。
ここでは、なぜ法律上の時効期間を過ぎても税金の支払いを免れることができないのか、その理由について解説します。
5年過ぎても納付義務は消えない
延滞税とは、税金が定められた期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、課される税金です。延滞税は、国税徴収法により、原則5年で時効が適用されます。
税務署や自治体が、滞納している税金を5年間放置していれば、5年で時効が成立します。
しかし現実には、滞納した税金を支払うよう支払督促や仮差押えを行うのが一般的です。
このように、支払督促や仮差押えなどを行使することで時効はリセットし、新たに5年の時効がスタートします。
天災など、一部の事由を除き、支払督促や仮差押えなどを行使していれば、5年を過ぎても納税義務は消えない点に注意しましょう。
滞納で財産の差し押さえが行われるまでの流れ

税金を滞納した場合、直ちに差し押さえが行われるわけではありません。納付を促す通知や督促が段階的に行われるのが一般的です。
それでも通知等を無視し、滞納し続けた場合に限り、最終的な手段として差し押さえが実施されます。
以下では、滞納から差し押さえまでの一連の流れについて解説します。
| 1 | 延滞税の発生 | 納期限の翌日から自動的に延滞税が発生します。 |
↓
| 2 | 督促状の送付 | 原則として、国税の場合は納期限から50日以内に、地方税の場合は納期限から20日以内に督促状が送付されます。 |
↓
| 3 | 予告書による滞納処分(差し押さえ)の執行通知 | 督促状を発送した日から10日を経過し、無視し続けていると、財産差し押さえの予告として通知書が送られてきます。 |
↓
| 4 | 財産調査 | 財産差し押さえの予告としての通知書が送付されているにもかかわらず、まだ税金の納付が行われていない場合、財産調査が実施されます。 |
↓
| 5 | 滞納処分の執行(差し押さえ) | 財産調査の実施により、差し押さえができる財産があった場合、強制的に差し押さえが可能です。 |
前述の通り、延滞税は原則として納期限の翌日から発生し、納付日までの日数分が本税に加算されます。
督促状の送付以外にも、自治体によっては電話による督促を行ったり、自宅訪問をしたりするケースがあります。
財産調査において、滞納者自身が保有する財産を調査します。差し押さえが可能な財産は、預貯金や株式、不動産・生命保険などです。給与に関しては、手取りの4分の1まで差し押さえができます。
また、税金の滞納による差し押さえは、強制執行が可能です。裁判所での手続きが不要なため、差し押さえの予告から執行までの期間が短いケースがあります。
税金滞納で差し押さえられないための対処法

税金を滞納したからといって、すぐに差し押さえが行われるわけではありません。
しかし、放置すれば差し押さえのリスクは高まり、最終的には財産を失うことにもつながりかねません。
では、税金滞納で差し押さえを回避する方法としてどのような点があるのでしょうか。
以下の4点があるので、順を追って紹介します。
- 一刻も早く税金を納める
- 税務署や自治体に相談する
- 減免・猶予の申請を行う
- 借入先へのリスケを相談する
一刻も早く税金を納める
延滞税が膨らむ前に、できるだけ早く滞納している税金を納付することが必要です。
とはいえ、手元に現金がない場合は、何らかの形で資金を調達しなければなりません。
税金の滞納がある状態では、金融機関からの融資は基本的に望めません。したがって、信用力や納税状況を重視しない手段で資金を確保する必要があります。
たとえば、自己資金の捻出や親族・知人からの借り入れのほか、売掛債権がある場合、ファクタリングを活用するのも一つの方法です。
【ファクタリングとは】
ファクタリングとは、自社の保有している売掛債権を、ファクタリング会社に買い取ってもらうことで、期日前に現金化が可能な資金調達方法です。
ファクタリングには、売掛先に知られずに利用できる「2者間取引」と、売掛先の承諾等が必要な「3者間取引」の2つの形態があります。
ファクタリングを利用する場合、手数料を払う必要があります。
2者間取引は10%前後、3者間取引は1.2%~が相場です。
2者間取引は、売掛先の承諾が不要なため、早期の現金化が可能です。
ただし、ファクタリング会社は売掛先より直接回収できないため、未回収リスクが3者間取引より高いため、2者間取引は手数料が高めに設定されています。
3者間取引は、売掛先が直接ファクタリング会社に入金するため、未回収リスクが低く、手数料が低めに設定されているのが一般的です。
ファクタリングは、法律的には売掛債権の譲渡である、合法的な資金調達方法です。
負債を増やさずに現金を得られるので、赤字や債務超過といった財務状況に不安がある企業にも利用できます。
はじめてのファクタリングに不安を感じている方は、創業以来10年以上の実績を誇るJTCにご相談ください。豊富なノウハウを持つ担当者が、どのような疑問や不安にも丁寧に対応し、安心してご利用いただけるようサポートいたします。
公式サイトの無料スピード診断をご利用いただくと、調達額がその場でわかるのでおすすめです。
税務署や自治体に相談する
税金の納付が期限内に困難な場合は、納期限を過ぎる前に税務署や自治体へ相談することも対処法のひとつとしてあげられます。
すぐに納付ができない理由や、納税する意思があることを事前に伝え、納付可能な期限や分割での納付など、事情に合わせた支払い計画について相談することが重要です。
早めに相談することで、事業運営の立て直しにつながる方策につながるでしょう。
減免・猶予の申請を行う
税金を滞納した状態であれば、最終的には財産を差し押さえられます。しかし、事情によっては、申請すれば税金を減免してもらえたり、猶予を受けられたりすることが可能です。
減免・猶予してもらえる可能性がある事情として、以下のものがあります。
- 被災による損害がある
- 生活保護を受給している
- 失業(解雇・倒産)
- 学生
- 障害者
- 病気で多額の医療費がかかった
- 納税すると生活維持が困難
- ほかの税金は滞納していない
未納分よりも本人の資金が下回っていたり、多額の借金を抱えたりしていて、納税できる経済状況でない場合、減免してもらえる可能性が高くなります。
また、財産を売却や、経費削減などの対処をしても支払いが困難な場合も、減免の対象となる可能性もあります。
猶予や減免が認められるか否かはケースバイケースですが、納税の意思があることが前提である点に注意しましょう。
(参照:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ」)
借入先へのリスケを相談する
借入金の返済が重くのしかかり、納税が困難になっている場合は、借入先の金融機関に返済条件の見直し(リスケ)を相談することも、有効な対処法のひとつです。
新たに資金を調達して納税に充てるという手段もありますが、税金を滞納している状況では、そもそも審査の俎上に上がりません。
一方、リスケは新たな借入を伴わずに、資金繰りを改善できる手段であり、金融機関も原則として応じる姿勢を取っています。税金の滞納に悩む事業者にとって、現実的かつ効果的な選択肢となるでしょう。
ファクタリングでの資金調達はJTCにお任せ

税金の滞納には実質的な時効がないため、延滞税が膨らむ前にできるだけ早く納付してしまうのが賢明といえます。とはいえ、手元に納税資金がない場合は、ファクタリングの活用がおすすめです。
ファクタリングは融資でないので、信用情報に影響を与えずに資金調達できる方法です。
審査において、売掛先の信用力が重視されるため、赤字経営や税金の滞納がある状態でも資金調達ができます。
急ぎでまとまった現金を確保したいなら、JTCのファクタリングがおすすめです。
JTCを利用するメリットとして、以下の点があります。
- 最短即日での現金化が可能
- 上限買取可能金額が無制限
- 最低手数料が1.2%
- 土日祝日対応
- 対面、オンラインどちらも対応可能
JTCの公式サイトの無料スピード診断を利用いただくと、事前に買取可能金額がその場でわかります。買取金額がいくらなのか不安に思われる事業者様にはとても便利ですので、ぜひご利用ください。
調達額がその場でわかる
まとめ

税金の滞納は、延滞税の加算や財産の差し押さえ、信用力の低下といったデメリットをもたらします。同時に、新たな融資が受けられなくなり、結果としてキャッシュフローや事業の継続にも悪影響を及ぼしかねません。
滞納税金の時効が5年とされていても、実際に納付義務が消えることはほとんどないので、放置しないようにしましょう。
差し押さえを回避するためには、税務署や自治体への相談や、猶予や減免の申請、借入先とのリスケ交渉など早期の対応が大切です。ファクタリングなどにより資金を調達し、早期に納付するように心がけましょう。
JTCは2013年の創業以来、累計取扱金額500億円超、取扱件数1万件以上という豊富な実績を誇る信頼のファクタリング会社です。無料のスピード診断を利用すれば、手元の売掛債権がどの程度の資金が調達できるのかがすぐにわかり、急な資金ニーズにも迅速に対応できます。
資金繰りの改善やファクタリング会社選びでお悩みの事業者様は、上限金額の制限がないJTCの利用をぜひご検討ください。





