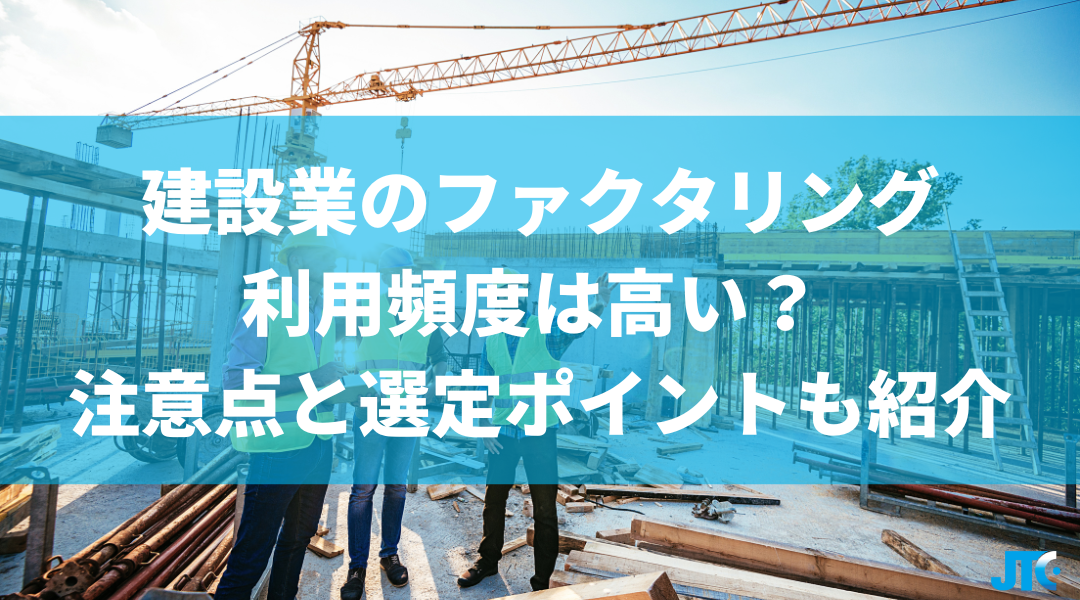建設業は、1回の受注額が大きくなりやすい一方で、建設資材や人員の確保で事前の出費も大きくなりやすい業種です。
資金繰りを改善する方法として、ファクタリングを利用する企業も増えつつあります。
この記事では、建設業とファクタリングの相性や、利用するときの注意点を解説します。
建設業でファクタリングの利用頻度は高い?
ファクタリングの利用頻度が高い業種には、「運転資金不足になりやすい」「売上の回収サイトが長期化しやすい」「納品までの期間が長い」といったいくつかの共通点があります。
建設業も上記の特徴をもっており、ファクタリングの利用頻度は高い業種です。
業界ならではの特徴として、自社以外の要因で売上の回収が遅くなる場合もあることがあげられます。
建設業の場合、巨大プロジェクトでは複数の会社で分担して工事を行うケースは珍しくありません。
ただでさえ工期が長く、報酬が支払われるまでに長い時間がかかる工事に複数社が関わると、他社が原因で予想外の遅延が生じる場合もあります。
国土交通省の調査によると、実際に工期が遅れた要因として、下記のように自社都合ではないものも多くあげられています。
- 警察との協議で昼間施工が夜間施工に変わった
- 設計書と現状の違いによる仕様・施工の見直し
- 設備機器やサイズ変更した資材の納入遅延
- 前工事・前工程の遅延による影響
- 電気配線工事の工期変更
(出典:国土交通省「建設工事における適正な工期の確保に向けて」)
自社が人材や工期をきちんと確保していても、前工事や前工程を担当していた他社が遅延すれば、自社にシワ寄せが来ます。
設計と現状にズレがあった場合も、仕様変更による資材の新たな発注が必要となり、資材納入やその後の工期遅延につながります。
上記の理由で工期の遅延が続けば続くほど、自社に原因がなくとも報酬を受け取るタイミングがズレてしまいます。
最終的に得られる売上が大きくても、入金されるまでに時間がかかれば、その間にかかる人件費や重機のリース代などは自社にある資金でまかなわなくてはなりません。
結果、「売上はあるものの現金がない」状態に陥ります。
運転資金をまかなうために、手元にある売掛債権をファクタリングで現金化する建設業は珍しくありません。
JTCのお客様にも、建設業の方は多くいらっしゃいます。
もちろん建設業以外の業種のお客様からのご相談も受け付けておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
建設業とファクタリングの相性がよい理由
資金調達の手段は、ファクタリング以外にも銀行融資やノンバンク系などさまざまな方法があげられます。
中でも手軽な方法としておすすめな資金調達方法が、売掛債権を利用するファクタリングです。
ここでは、建設業にファクタリングがおすすめな理由として、相性がよいポイントを解説します。
大型の案件を受注やすい
建設業は、数千万円や数億円の大型案件が発生することもあります。
ファクタリングは、大型の案件を受注しやすい業種におすすめの資金調達方法です。
大型案件を受注できる一方で、建設業は報酬を受け取るまでには日数がかかります。
前述のとおり、売上が入金されるまでの間は資材費や人件費、重機のリース代などの費用を、自社が先出ししなくてはなりません。
大型の場合は下請け会社に外注する場合もあり、発注時に前金の支払いが発生します。
そのため売上が大きい大型の案件を受注するためには、まず自社で前金やランニングコストをまかなえるほどの資金を用意する必要があります。
付き合いの長い取引先なら、相談していくつかの段階に分けて、工程ごとに代金を分割して受け取る方法もおすすめです。
ただし、必ずしも取引先が分割払いに応じてもらえるとは限りません。
手元に他の受注で発生した売掛債権があれば、分割払いしてもらわなくても、ファクタリングで現金を即座に用意できます。
下請けへの前金や人件費などのランニングコストにかかる費用を確保できるので、資金の心配をせず積極的に大型の案件を受注できるようになります。
急な出費に対応できる
ファクタリングは、急な出費への対応にも便利です。
建設業では、下記の理由で急な出費が発生することがあります。
- 突発的な工事の依頼
- 工事の途中で資材価格が高騰
- リースしている設備・機械の故障
建設業では、近年よくニュースとなっている設備の老朽化にともなう故障など、突発的な工事の依頼が舞い込むことがあります。
自社が受注するためには、資材や人材をかき集めるための現金が必要です。
工事の途中で資材価格が高騰した場合も、当初予定していた予算では足りなくなるおそれがあり、突発的な出費につながります。
資材を追加納入するとき、あらかじめ用意していた現金でまかなえない場合は、更に現金を用意しなくてはなりません。
リース品の故障も、突発的な出費の要因の1つです。
建設業では、重機などの高額動産をリースしていることが珍しくありません。
リースしている重機や事務所などの設備を作業中の事故で故障させた場合、契約内容によっては負担金を支払うこととなります。
リース会社では補償制度を用意しており、契約時に強制加入することもあるものの、補償を利用しても一部負担金が発生することがあるため、注意が必要です。
負担金は数万円で済む場合もあれば数百万円かかることもあり、故障内容によっては大きな出費となるでしょう。
ファクタリングなら、まとまった額の出費が急に発生しても、短期間で資金調達できます。
負債を生まずに資金調達できる
ファクタリングのメリットは、負債を生まずに資金調達できることです。
企業の主な資金調達の1つが、銀行融資です。
しかし銀行融資は審査に時間がかかるうえ、必ずしも借入できるとは限りません。
借りられたとしても自社の負債を増やすことになるため、不安定な経営状況をさらに悪化させるおそれがあります。
ファクタリングは、もともと保有している売掛債権を売却して現金化する方法です。
帳簿上も負債にはならないため、企業の社会的信用を落とす心配がありません。
借入ではなく、将来的に得られる売上の回収サイトを短縮しているだけなので、利息の支払いや返済の必要もないのが魅力です。
建設業のファクタリング利用時の注意点
ここでは、建設業がファクタリングを利用するとき、どのような点に注意するべきか解説します。
手数料が発生する
ファクタリングは借金ではないため、利息や元本の支払い・返済は発生しないものの、売掛債権の買取に対する手数料は発生します。
手数料の料率に業界的なルールはなく、ファクタリング会社ごとに異なります。
また、取引方法によっても手数料は変わるので、注意が必要です。
ファクタリングの取引方法には、2者間取引と3者間取引の2種類があります。
| 2者間取引 | ファクタリング会社と申込者のみで行われる取引です。売掛先からの承諾を得る必要がなく、現金化のスピードが比較的早い傾向があります。 |
| 3者間取引 | ファクタリング会社、申込者、売掛先の3社が関わる取引方法です。申込者は、事前に売掛先へファクタリングを利用することを承諾してもらう必要があります。 |
取引方法で見ると、3者間取引のほうが手数料は安くなる傾向です。
3者間取引は売掛先にファクタリングを利用することを通知する分、未回収リスクなどのトラブルが起こる可能性が低くなるため、多くのファクタリング会社で安く設定されています。
取引方法ごとの平均的な手数料は、2者間取引が約10%、3者間取引が約1.2%~です。
ファクタリング会社によっては、上記以上の手数料となることもあります。
少しでも多くの資金を調達したいなら、手数料がいくらに設定されているのかにも注目しましょう。
売掛先の経営状況によっては断られる場合がある
売掛先の経営状況が良くないと判断されると、ファクタリング利用を断られる可能性があります。
ファクタリングの審査におけるメリットは、自社ではなく売掛先(取引先)の経営状況が重視されることです。
自社が仮に赤字経営でも、売掛先の経営が安定していれば審査に通過しやすくなります。
しかし見方を変えると、自社が黒字経営でも売掛先の経営状況が悪ければ、ファクタリング会社に利用を断られるリスクがあるとも言えます。
建設業は1件の案件で得られる売上が大きい分、資材費や人件費など出て行くお金も大きい業種です。
業界全体的に、経営が不安定化しやすい傾向です。
ファクタリングを利用するときは、売掛先の経営状況も考慮する必要があります。
調達できるのは売掛金の額面まで
ファクタリングは売掛債権の売却という性質上、売掛金の額面以上の資金は調達できません。
まとまった金額を調達したいときは、額面の大きな売掛債権を持ち込むか、複数の売掛債権を売却する必要があります。
加えて、ファクタリング会社ごとに対応できる金額の上限・下限が異なります。
相談しても額面が小さい・大きいことを理由に「うちでは買い取れない」と申し込み自体を断られるかもしれません。
建設業は売掛債権の額面が大きくなりやすいので、対応できるファクタリング会社には限りがあります。
事前に問い合わせるか、公式サイトで買取可能な額面の範囲を確認しておきましょう。
JTCは、下限100万円から、上限なしで買い取っております。
売掛金の額面の範囲内なら、建設業の高額な売掛債権もご相談いただけます。
売掛先との取引に影響が出る場合がある
前述のとおり、ファクタリングの3者間取引は、売掛先にファクタリング利用を承諾してもらう必要があります。
売掛先に余計な費用がかかるわけではないため、承諾してもらえる可能性が高いものの、中にはファクタリング利用そのものに不安を抱く担当者もいます。
「売掛金の回収サイトを短縮する=経営状況が悪いのでは」と怪しまれれば、今後の取引に影響が出かねません。
売掛先に知られると今度の契約に影響が出そうな場合は、2者間取引を検討してみてはいかがでしょうか。
すべてのファクタリング会社が2者間取引を受け付けているわけではないため、利用するときは事前に対応可能か確認しておくことが大切です。
JTCなら、2者間取引にも3者間取引にも対応しております。
お客様の事情や要望をヒアリングしたうえで最適な方法を提案しますので、お気軽にご相談ください。
建設業のファクタリング会社選びのポイント
ファクタリングで満足度の高い取引ができるかどうかは、会社選びにかかっています。
ここでは、建設業のファクタリング会社選びについて、重視すべきポイントを4つ解説します。
適切な手数料のファクタリング会社を選ぶ
ファクタリングを利用するときは、手数料も考慮して契約先を選ぶことが大切です。
建設業は1件ごとの売掛債権が高額となりやすいため、料率のわずかな差で支払う手数料は大きく変わります。
仮に1億円のファクタリングなら、手数料10%の場合は1,000万円、1.2%の場合は120万円となり、手数料だけで880万円もの差が生じます。
少しでも得られる現金を増やすためには、手数料が安いところ・安い取引方法を選びましょう。
ただし、安すぎる業者は悪徳業者だったり別の名目で費用を請求したりしているリスクもあります。
手数料の安さだけを見て選ばないことも、損をしないコツです。
適切な手数料を知る方法として、相見積もりがおすすめです。
相見積もりで複数のファクタリング会社の手数料を確認して、平均的な金額を知ると判断しやすくなります。
JTCは、公式サイトで無料スピード診断を提供しております。
無料スピード診断なら、相談前に自社がいくら調達できるか分かるので安心です。
「一度問い合わせると断りにくい」という方も、事前に調達額が分かる無料スピード診断なら安心してご利用いただけます。
入金スピードの早い会社を選ぶ
ファクタリングは、急な出費で現金が必要になった場合に利用することが多いサービスです。
しかしファクタリング会社によっては、審査に時間がかかって入金まで数日かかるところもあるので注意しましょう。
入金スピードの早いファクタリング会社を選べば、「明日までに必要」「月曜には入金してほしい」というときも間に合わせられます。
JTCは、最短即日での入金が可能です。
お客様の要望に応じて、土日祝日も相談に対応しております。
「とにかく早く現金化してほしい」という方も、まずはお問い合わせください。
初回は原則対面での相談が必要ですが、2回目以降のご利用は、状況に応じてオンラインでのご相談にも対応できます。
書類提出もLINEを利用してオンライン提出できるので、忙しい経営者の方でも隙間時間でお手続きいただけます。
支払期限が長い売掛金に対応できる会社を選ぶ
建設業の売掛債権は、支払期限が長く設定される傾向にあります。
売掛債権の買取時、ファクタリング会社が確認する要素の1つが、支払期限(回収サイト)の長さです。
ファクタリング会社によっては、支払期限が長い売掛債権は買い取ってもらえないことがあります。
回収サイトが長期化しやすい売掛債権でも買い取ってくれるファクタリング会社なら、建設業の方も気軽に利用できます。
建設業でのファクタリング実績がある会社を選ぶ
ファクタリング会社を選ぶときは、すでに建設業での取引実績があるところがおすすめです。
建設業でのファクタリング実績が豊富な会社なら、額面が大きい売掛債権でも買い取ってもらえる可能性が高いと言えます。
建設業界の事業についてもある程度知っているので、業界ならではの悩みも相談しやすくなります。
JTCは、幅広い業種のお客様からご利用いただいています。
建設業のお客様のご利用も多く、実績が豊富にありますので、安心してお任せください。
建設業におけるJTCの実績
JTCは、業種問わず多くのお客様にご利用いただいております。
建設業のお客様がJTCにて調達された(債権譲渡された)資金の実績は、下記のとおりです。
| 過去取引実績 |
最低契約金額:130万円 最高契約金額:2億8200万円 |
上記以外の額面の売掛金にも対応しておりますので、「3億円の売掛金があるんだけど」「急ぎで10億の売掛債権を現金化したいんだけど」という方も、お気軽にご相談ください。
まとめ
建設業は、1回の受注で発生する売掛金の額が高いため、ファクタリングでまとまった現金を調達できます。
ただし、建設業の高額な売掛債権は買い取れないファクタリング会社もあるので、注意が必要です。
JTCは、多くの建設業のお客様からもご利用いただいています。
売掛金の額面の範囲なら、高額の買取にも対応しておりますので、一度ぜひご相談ください。
事前にいくら調達可能なのかが分かる、無料スピード診断もぜひお試しください。