事業運営において、資金調達は欠かせません。仕入資金の支払いや人件費の支払い、商品を製造するための機械購入など、事業の継続と成長には財源の確保が必要です。
資金が調達できなければ、事業の拡大はおろか、支払いが滞り、最悪の場合には資金ショートによる倒産リスクも生じます。では、企業はどのように資金を調達し、適切な金額を算出すればよいのでしょうか。
本記事では、事業資金を借り入れる際の基準について解説します。短期・長期借入金の違いや目的別の借入金額の相場、さらに借入可能額を判断する基準も紹介しますので、借入金額に迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
調達額がその場でわかる
監修者プロフィール

急遽資金が必要になった、新規事業開拓のための資金が欲しい、経営状態に関する相談がしたい、そんな経営者の皆様を全力でサポートしています。
短期借入金と長期借入金の違い
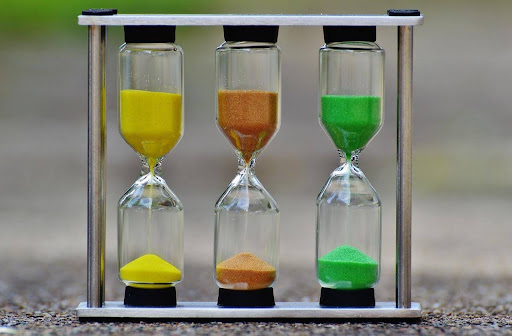
事業運営における資金調達方法には借入(融資)があり、「短期借入金」「長期借入金」があります。2つの借入金の分類基準は、返済期間です。
短期借入金は返済期間が1年以内の借入で、長期借入金は、1年以上の借入期間です。
貸借対照表において、資産または負債を流動あるいは固定に区分する会計ルールを「ワン・イヤー・ルール(一年基準)」とよんでいます。
企業の資金繰りへの影響や支払い能力を調べる方法として使われる指標に「流動比率」や「当座比率」が用いられます。
流動比率は、「流動資産 ÷ 流動負債 × 100」で計算し、1年以内に現金化が可能な流動資産と、1年以内に支払う必要のある流動負債の割合がどれくらいであるのかをみる指標です。流動資産が流動負債を上回っている状態、つまり、100%を超えている状態が望ましいです。
また当座比率は「当座資産(現金・預金・売掛金) ÷ 流動負債 × 100」で算出されます。
当座資産とは、現金や預金、売掛金といった、流動資産の中でも流動性の高い資産をさします。当座比率は、短期返済能力をみる指標であるので、100%以上あることが望ましいです。逆に、100%を切っている場合、資金がショートする恐れがあるので注意が必要です。
短期借入金・長期借入金のメリット・デメリットとして、以下の点があります。
【短期借入金・長期借入金それぞれのメリット・デメリット】
| メリット | デメリット | |
| 短期借入金 | ・金利が低い傾向にある ・審査が比較的緩め |
・一回当たりの返済金額が大きい ・返済が厳しくなる恐れがある |
| 長期借入金 | ・毎月の返済負担が軽い ・計画的な返済が見込まれる |
・金利負担が長期化する ・審査が厳しくなる |
短期借入金は借入期間が短いため、金融機関にとって未回収となるリスクが低いです。そのため、金利が低めに設定される傾向にあり、比較的審査も緩めです。短期借入金は返済金額が大きくなるため、売掛債権の回収が厳しくなると、返済が厳しくなる恐れがあります。
長期借入金は、長期にわたって返済するので、毎月の返済が楽であり、計画的な返済が可能です。一方で、金融機関にとって未回収リスクが高くなるため、審査が厳しくなる傾向にあります。長期間の返済であるため、企業にとって金利負担が大きくなります。
借入金の相場
日本政策金融公庫や、制度融資では、借入限度額が設定されているのが一般的です。しかし、どの企業も借入限度額いっぱいまで利用できるわけではありません。企業の規模や業績によって利用できる資金調達金額が異なるのが一般的です。
また、資金調達できる金額は、資金目的により算出方法がさまざまです。
ここでは、以下の状況における借入金額の目安について解説します。
-
- 開業資金として借り入れる場合
- 運転資金として借り入れる場合
- 設備資金として借り入れる場合
- 追加融資として借り入れる場合
開業資金として借り入れる場合
| 年度 | 融資の金額(平均) |
| 2014 | 928万円 |
| 2015 | 866万円 |
| 2016 | 931万円 |
| 2017 | 891万円 |
| 2018 | 859万円 |
| 2019 | 847万円 |
| 2020 | 825万円 |
| 2021 | 803万円 |
| 2022 | 882万円 |
| 2023 | 768万円 |
(参考:日本政策金融公庫「2023年度新規開業実態調査」)
日本政策金融公庫によると、2023年度における開業時の資金調達額は平均1,180万円で、そのうち金融機関や公的機関からの借入金は平均768万円でした。
また過去10年間のデータから、創業者への融資の金額は750万円〜900万円前後で推移しており、全体的に少額化傾向にあります。
開業時に苦労したこととして、資金繰り、資金調達をあげている経営者が59.6%ともっとも多い結果となっています。
(引用:日本政策金融公庫「2023年度新規開業実態調査」)
実際にどの程度借入すべきかといった具体的な金額に関しては、後述する計算式を利用することをおすすめします。
関連記事:運送業の開業資金は無担保・無保証で借入!開業に必要な金額は?
運転資金として借り入れる場合
仕入資金や人件費など、事業運営に不可欠な資金である運転資金の借入を検討する場合、一般的には月商の3か月分を目安とされています。売掛債権の回収の遅れや、予期せぬ出費などが発生した場合でも、事業継続できる資金を確保しておくためです。
ただし、業種や企業の規模によって適正とされる借入金の割合は変動するので注意しなければなりません。安定した収益が見込める業種では0.8か月分、季節変動が大きい業種では1.5か月分が適切とされるケースもあります。
運転資金の借り入れは、必要以上に借入を行うと金利負担が増え、少なすぎると事業運営に支障をきたす恐れがあるので、自社の状況に応じた慎重な資金計画を立てることが重要です。
設備資金として借り入れる場合
新しい機械や設備の導入や、店舗・車両の購入といった設備資金を借入する場合、設備を導入することで見込まれる売上金が審査の基準となります。
目安となる設備資金金額を算出する方法として以下2点があります。
|
ただし、業種や導入する設備の種類、企業の資産や負債の状況により適正な金額は変動する点に注意しましょう。
注意点として、設備資金は売上見込額をベースとするため、見込額が甘いと審査に通らなかったり、返済に支障をきたしたりする恐れがあります。設備資金として借入する場合、十分な事業計画を策定することが重要です。
追加融資として借り入れる場合
すでに同じ金融機関で融資を受けている場合、これまでの返済実績が追加融資の可否に大きく影響します。
例えば、1,000万円を借りた企業が300万円を返済済みであれば、その範囲内である300万円程度までの追加融資を受けやすくなります。ただし、金融機関ごとに条件が設けられているため、事前に詳細を確認することが重要です。
追加融資の条件の参考として、日本政策金融公庫の場合を紹介します。追加融資の条件は以下の通りです。
|
既存融資を返済していることは、返済実績として考えられるため、信頼を高める要因となります。経営状態が芳しくなければ、追加融資は厳しいです。収益性やキャッシュフローが良好であることが求められます。
前回の融資が希望額未満だった場合、減額された原因を解消していなければなりません。
どうして追加の資金が必要なのかを明確にし、事業計画に沿った合理的な理由が必要です。
また、追加融資を検討する際には、事業の安定性や成長見込みを冷静に分析し、過剰な借り入れによる返済負担を回避することが重要です。
自分がいくら借り入れられるか調べる方法
これまでは、借入金額の算出基準として、月商や売上予測、返済実績を用いてきました。
より具体的に借入金額を計算する場合、決算書上での数字を使う方法があります。
以下の数値を基準として借入金額を調べる方法を、ここでは紹介します。
- 経常利益を基準にした計算方法
- 借入依存度を基準にした計算方法
- 債務償還年数を基準にした計算方法
経常利益を基準にした計算方法
経常利益は、企業が事業運営において、いくら儲けているのかの数値です。経常利益を基準として、借入金額を算出する方法があります。
経常利益を利用して借入金額を算出する場合、以下の式を使います。
| 融資を受けられる上限額=直近3期の経常利益平均×50%×7 |
この計算式は、企業の儲けである経常利益の半分を使って、7年間で返済することを示します。例えば、平均経常利益が500万円の場合、融資可能な金額の上限は1,750万円です。
企業の収益力に基づいた合理的な判断を行えるため、シビアな数字を把握するのに適しています。特に中小企業では、無理のない借入計画を立てる上で大いに役立つでしょう。
借入依存度を基準にした計算方法
借入依存度を利用して、融資金額を調べることが可能です。借入依存度とは、総資産に対して、借入金がどれくらいあるのかの割合を示す、企業の健全性を調べるために使われる指標です。
借入金依存度は以下の計算式で求められます。
| 借入依存度=借入金額(長期借入金+短期借入金+割引手形+社債など)÷総資産 |
通常、借入金依存度の目安として、30%以下が健全とされています。また、50%前後から危険な状態とされているので、総資産の50%までに借入金額を抑えることが必要です。
そのため、融資の上限金額は、以下のように算出します。
| 融資の上限金額=総資本 × 50% |
この計算式は、追加借入が可能かどうかも判断できるので、無理のない資金計画が立てられます。
債務償還年数を基準にした計算方法
債務償還年数とは、企業が借入金を返済するのに要する期間を表す指標で、返済能力を測る基準として活用され、以下の計算式で算出できます。
| 債務償還年数=総借入額 ÷(当期純利益+減価償却費) |
総借入額が、企業の返済原資である当期純利益と減価償却費の合計金額により、何年で償還できるのかが計算できます。
債務償還年数は、通常10年以内であれば妥当な財務状態とされています。一方、債務償還年数が10年超になると、金融機関はリスクが高いと判断するため、借り入れは厳しくなるでしょう。
債務償還年数を基準にすることで、収益力や資金運用を具体的な数字で把握でき、過大な借入を防ぐことが可能となります。
借り入れの準備は2か月前から行動しよう
事業資金が必要になってから慌てて動くと、時間が足りなくなる恐れがあります。
融資には審査があり、実際に資金調達できるまで1ヶ月近く時間がかかります。
そのため、借入による資金調達を検討する場合、遅くとも1~2か月前から準備しなければなりません。
事前に必要書類を準備し、計画的に金融機関との交渉を進めることで、スムーズな借入が見込まれます。時間に余裕をもって行動することが大事です。
急ぎの資金調達はファクタリングがおすすめ
事業運営していると、計画的に資金繰りを進めていても、突然現金が必要になることがあります。融資を申し込んでも、審査や手続きに時間を要し、急な資金調達に対応できない場合があります。急な資金調達におすすめなのがファクタリングです。
ファクタリングとは、売掛債権を早期に現金化する仕組みで、融資とは異なり借金ではありません。そのため、負債として計上されないメリットがあり、企業の安全性を低下させることはありません。
JTCのファクタリングは、業界最安水準の手数料で、買取金額に上限なし利用できます。公式サイトの「無料スピード診断」を使うことで、事前にどれだけの資金が調達できるかを簡単に確認できます。
急な出費には、JTCのファクタリングを検討してみてはいかがでしょうか。手軽でスピーディーな現金化が、貴社の資金繰りを強力にサポートします。
調達額がその場でわかる
まとめ
借入金には短期と長期の違いがあり、それぞれ資金用途や返済期間が異なります。借入金の相場は、開業資金・運転資金・設備資金・追加融資など、資金使途によって異なります。
自社の資金目的に応じた金額を算出することが必要です。
自社がどれだけ借り入れできるのかを事前に把握することも重要です。経常利益や借入依存度、債務償還年数といった基準を活用することで計算できます。
借り入れ準備を行う場合、審査に時間がかかることを踏まえ、余裕をもって進めることをおすすめします。とはいえ、急な出費が発生した場合、融資で対応できないことが起こるかもしれません。急な出費が発生した場合、おすすめなのは、売掛債権を早期に現金化できるファクタリングです。
JTCは、最短一日で現金化が可能なファクタリング会社です。土日祝日も、経験豊富なスタッフが対応しているため、平日事業で忙しい事業者も安心して利用できます。
公式サイトの「無料スピード診断」を使うことで、事前に資金調達金額の把握が可能です。
JTCは、がんばる企業の資金繰りを全力でバックアップします。事業運営のパートナーとして、JTCを利用してみてはいかがでしょうか。


